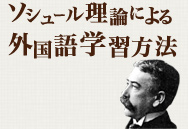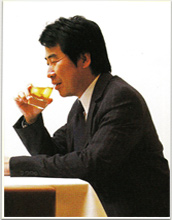恋愛結婚か見合い結婚か?
2019-11-20 (水)
国立社会保障人口問題研究所の調べでは、現在の見合い結婚の比率は5.5%。戦前7割を超えていたのが、60年代後半に逆転し今はほとんどが恋愛結婚のようだ。
歴史的にみると、どの国でも古くは見合い結婚がほとんどでようだ。お隣の韓国では、同じ氏族の中では結婚は許されなかったようで、つまり同じ苗字の人とははなから結婚できない訳だ。同じ苗字と言っても、韓国で苗字は極端に少ないし、昔は同じ地域に住む人はほとんど同じ苗字だったようなので、同じ地域に住む人とは結婚できない、ということだった。同じ地域に住むひと同士で結婚できないので、当然遠隔地に住む違う氏族の親同士が話し合って結婚を決めていて当然見合い結婚だった。これは、結婚とは、違う地域に住む氏族同士が血縁になって平和への一助となる社会行為であったと換言できる。日本でもテレビ時代劇をみると、武家の婚礼は家と家が縁を結ぶためのもので、つまり見合い(政略)結婚がほとんどだと思われる。
韓国の新興キリスト教である、世界統一協会は国際政略結婚とも言える、教祖が決めた相手と国際結婚するというルールで世界平和や社会平和を実現することを旨としているが、韓国伝統の考え方に基づいているのではないか。
ではさらに古く遡って農耕が始まる前の狩猟時代はどうだったを考えてみると、少し前までは原始乱婚という、出会い頭に生殖を行うような社会であったと思われていたが、最近の研究ではどうもそうではなさそうで、むしろ今より厳格なルールがあったことが最近の定説だ。
民族学者で哲学者のレヴィストロースは狩猟時代の社会システムが残るブラジル奥地に住む先住民族のインディオ社会に潜入し、そこでの結婚に関するしきたりを研究した。この研究は後に世界的にもっとも影響力を持つ思想である「構造主義」の契機になる。この時の経験を書いた彼の著作「悲しき熱帯」は世界的ベストセラーになった。
レヴィストロースは見合い結婚(=政略結婚≒親族の成り立ち)を研究することによって、その社会の構図を明かにした。結論から先に言えば、「女性は部族間の贈り物であった」とストロースは発見した。(これは歴史社会学の結論で、女性蔑視ではありません)。こう考えるとそれまで説明がつかなかった世界的に見られる同じ氏族内での結婚忌諱(広い意味でのインセント(近親婚)タブー)が全て説明がついた。(くわしく知りたい人は、橋爪大三郎の「初めての構造主義」や小田亮の「レヴィストロース入門」を読んでください。)
さて、「見合い結婚」が部族間の平和の礎であったことを考えると、現代に於いては、同じ国内での諍いは司法や行政の力で抑えられているので、必要なく憲法にあるように本人どうしの合意で結婚できるということになって、94.5%が恋愛結婚という時代が来たよだ。
しかし、この恋愛結婚であるが、厳密な意味で恋愛結婚と言えるのだろうか?憲法では本人どうしの合意で結婚できるとあるが、恋愛結婚で結婚できるとは書いていない。本人どうしの見合い結婚という事は一見内容に見えるが、見合い結婚を政略結婚と読み替えると、本人どうしの政略結婚というのは案外多いような気がする。
最近デヴィ夫人の著作を立ち読みしたが、その本に「年収に二億でそんなに惹かれない男と年収200万円で惹かれる男をどちらと結婚すべきか」という章があった。女性の皆さん、あなたはどちら?
現代でも女性が贈り物だとすれば、現代における見合い(=政略≒打算)結婚を選ぶ人は、自分という贈り物を誰に送るか、ということになる。デヴィ夫人は年収に二億の男と結婚せよ、といっている。何しろ自分がインドネシア大統領の第三夫人になったひとだものね。
ジェンダーとしてのメスは、より多くの自分の遺伝子を残す戦略として、なるべく質のよい遺伝子を残すという遺伝子選択の戦略と、出産後に安全に育児できるかという安全性確保の戦略とのバランスでオスを選んでいる。オスは単純なもので、より多くのメスに自分の遺伝子を残すのが戦略である。
人間の例を考えると、女性は一年に一回しか妊娠出来ず、さらに出産しても15年以上育児に費やさなければならないので、大変なリスクを負っている。出産後の安全性確保ゆういの種と言える。
さて、見合い結婚と恋愛結婚に話を戻すと、自分自身を贈り物として政略的に結婚するつまり、よく言われる高学歴、高収入の男性と結婚するのは一種の政略結婚(=見合い結婚)とくくり、純粋に惚れた男と結婚するのを恋愛結婚と定義し直せば、世の8割くらいが見合い結婚といえるのではないか?
さて、あなたはどちら?