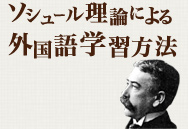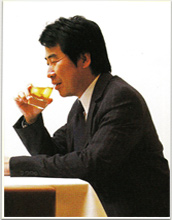谷田の婆さんは不幸だったのか?
2019-11-12 (火)
父は昔、90歳を超えてかも、毎日忙しくしていた。ゴミ出し、洗濯に始まり、掃除は徹底していて、近所の人に掃除を推奨して煙たがられている。年を考えて少し休めばいいのにと思ったものだ。
その父がよく、昔話をした。これが結構おもしろかった。ある時、「谷田さんの婆さんは苦労した」という話を聞いた。谷田さんの婆さんは、親父の母方の叔母さんだ。私からみれば、祖母の妹で大叔母。この人のことはよく覚えているが、祖母によく似ていて、祖母が死んだ後も、この人を見るたび祖母を思い出し懐かしい感じがした。
谷田の婆さんは、乳母日傘で育てられたいいところのお嬢さんだった。兼業農家で食堂も営む谷田さんのところに30半ばを超え嫁いだ。谷田の婆さんの夫、谷田の爺さんは谷田の婆さんと結構する前、婆さんの姉と結構していて死別した。つまり谷田の爺さんは先妻の妹と結婚したわけだ。
姑はかなり厳しい人だったそうで、谷田の婆さんは嫁時代に完成度の高い家事を仕込まれ、四六時中姑に叱られていたそうだ。谷田の爺さんは食堂を経営していたので、畑は婆さんが一人で切り盛りし、同時に血筋で見ると自分の甥たちを息子として育てた。厳しい人生だったに違いない。
苦労はしたのだろうが私が覚えている谷田の婆さんは、文字通り婆さんでその顔はいつも穏やかで微笑んでいた。
ゴータマシ―タールダ(釈迦)は、王子だった。父親の王は何不自由ない生活をさせていたと伝えられている。何でも欲しいものは手に入り、おいしい食事、美しい妻と可愛い息子に恵まれ、上げ膳据え膳であったに違いない。
筆者も釈迦とは比べようもないが、両親のおかげで子供の頃は何不自由ない生活を送った。青春期も欲しいものはなんでも手に入り、日常の不自由は全くなかった。日常に悩みがなくなると人間悩みを探すもので、当時、人間は死んだらどうなるのか?とか、病気になるのではないか?とか、人に危害を加えてしまうのではないかとか、そのうち、手を洗わないと汚いのではないかと2時間も3時間も手を洗ったり、風呂に一日5回も6回も入ったりして、どうにもこうにもにも、身動きが取れなくなり、都立松沢病院の精神科に行ったら、脅迫神経症と診断され、森田療法がいいと勧められ、鈴木知準先生を紹介され治療をうけることになった。
治療は主に農作業、炊事、洗濯、風呂焚き、買い物など雑用を徹底的にしかも完成度高くやらされる。ミスをすると先生に叱られるので、必死に薔薇や朝顔の世話をしたり、集中して薪木で風呂をたいたりした。あとで知ったが、禅寺でも作務といって同じようなことをするらしい。
入院して1か月ほどすると、日常の忙しさに集中している自分がいて、高尚な悩みはどこかへ飛んで行ってしまった。それどころか、畑仕事や炊事を懸命にしていると、カタルシスさえ感じた。
日常に不自由なく、悩んでいたときの自分は出家まえの釈迦に相通じるところがあり、入院中の自分は不自由ない暮らしを捨てて修行に励んだ釈迦に似ている。そして、はっと気づいたのは入院生活は谷田の婆さんの暮らしに似ていた。
やることが無いというのはつらい。哲学者のカントの寝室の天井には「ここで考え事をするべからず」と大きく書いてあったどうだ。彼は、寝室での退屈をおそれ、朝布団に長居せず早朝に飛び起き、散歩にでかけ、一日中にひっきりなしに歩き回っていた。イギリスの思想家B・ラッセルは、「仕事のについて」という随筆の中で、「仕事から得られる最も大きな恩恵は、時間を潰せることである」と述べている。東洋でも中国古典、四書五教の一つ「大学」には、「小人閑居して、不善をなす」とある。「凡人、暇をしているとろくなことをしない」という意味である。
確か柳葉敏郎と石野真子主演の近未来SFドラマがであったと思うが、核戦争後の世界が舞台。生き残った人は放射能のまん延する廃墟に囲まれ、外出もままならず、時間を持て余しながら保存食を食べている。
そんな中自分の財産の半分を支払ってリアルで幸福な夢を見させるというサービスがあり、主人公の柳葉敏郎はサービスを受けることにして、その会社の部屋で注射を打たれる。そして、目を開けると石野真子扮する妻がいて、何やら慌てている。娘が肺炎で死にそうだとの事。深夜に必死に車を飛ばして病院を駆けまわるがどこも受け入れてくれない。やっとの思いで娘を入院させて、朝になると、家に借金取りが押し寄せてくる。経営している会社が倒産寸前なのだ。そうこうしているうちに自分が癌になって5年生存率は50%と言われる。癌を抱えながら会社立て直しの為に銀行をはいずり回り、借金を無心するが断られ続けたところで目が覚める。
核戦争後の現実の世界に戻った主人公はひとこと、「とても幸せな夢でした。」見ていて納得してしまった。谷田の婆さんもさぞ幸せだったに違いない。親父が齢90歳にして毎日忙しくしている理由がわかった。

 思考の壁と呼び変えても良いかもしれませんね。例えば、男性でも上半身裸で銀座の街を平日に歩く事に少し抵抗があひとが大多数と思います。でも夏のビーチなら問題ない。会社で男同士で会議室で裸になるのは恥ずかしいけど、ゴルフの後に一緒に風呂に入るには何の抵抗もない。
思考の壁と呼び変えても良いかもしれませんね。例えば、男性でも上半身裸で銀座の街を平日に歩く事に少し抵抗があひとが大多数と思います。でも夏のビーチなら問題ない。会社で男同士で会議室で裸になるのは恥ずかしいけど、ゴルフの後に一緒に風呂に入るには何の抵抗もない。